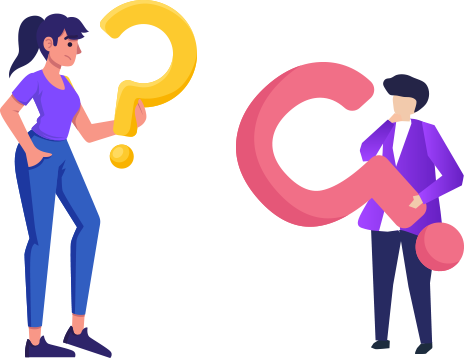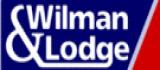What is FurnBids?
FurnBids connects bulk furniture buyers with homes being sold where the furniture is likely to be unwanted within the home transaction.
Who is it for?
FurnBids is generally built for buyers who purchase furniture in high volumes. Some examples are: used furniture retailers, clearance and house-clearance operators, property staging companies, exporters and refurbishers.
Are furniture items guaranteed to be available?
No, availability can depend on: seller preference, timing of the property sale, home buyer preference, etc. Express interest early to confirm all the details you require for bidding.
Can anyone register?
No, membership is limited to business accounts for qualified furniture buyers. Contact us for details.